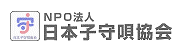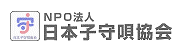DVと、女性と、生きる路
●離婚発表であらわれた有象無象
今から18年ぐらい前になるでしょうか。私は前の夫と離婚しました。日本中がひっくり返るほどの大騒ぎになり、そのときに初めて不倫という言葉が新聞紙上に出て、私自身もびっくりしたことを覚えています。熟年離婚という言葉のはしりでもありました。
予想外に感じたのは、離婚の原因は夫婦で様々にあるわけですが、私の不倫が100%の原因であり、夫はそれを容認したという形の離婚記者会見がされたことです。その時点で、私に降りかかってきた火の粉の凄まじさといったら、想像を絶するものでした。連日、マスコミでは姑を巻き込んでの報道がなされ、その間私はぼんやりと、とある一室に閉じこもっていました。
当時、私はメディアの仕事をしていましたし、劇団という公の仕事もしていましたから、自分の身を守るということは、人前に出ないことだと決めていました。たぶん表に出れば、蜂の巣をつついたような騒ぎになり、あらゆることをああでもないこうでもないと言われたり書き立てられて、最終的にはボロボロになるのは自分だと、わかっていました。見ない、言わない、聞かないと決めて、田舎に引っ込んでいました。
それでも、自分に関する報道を連日テレビで見るわけですから、ときには腹が立つというか髪の毛をむしりたくなるような状況もありました。全然見たこともない人が親友と称して登場したり、会ったこともない編集者が、あの奥さんはああだ、こうだったとあたかも、見てきたことのように、話していました。そして、まだ一緒になることをその時点では決めていなかった男性のところに、記者が張り付いているのを知ったとき、これはこの目でしっかりと事態を確かめよう、と覚悟はしました。しかし、この先自分が生きられるだろうかということを考えたら不安でいっぱいでした。
前の夫が悪いということではないのですが、私には私生活なんか全くないほど忙しい毎日で、相当な疲労がたまっていたと思います。金属疲労のように。
ちょうど更年期がぶつかったと、今になってみると非常にはっきりとわかります。
けれど、実際に前夫の家庭内暴力が離婚への大きな引き金になったことは事実です。
そのことに関してはどこにも、1字も書かれたことはないし、言われたこともありません。むしろ逆に、それとは違うことを誇大化し、悪いのはみんな女房で苦労してかわいそうな有名人の夫という図式を作ったのは、彼自身ではなく、メディアと巨大な力だったと思っています。当時は、ベストセラーの作家は出版社にとって金のなる木、傷つけてはいけない存在だったのです。ほんの売り上げでも落ちてしまったら大変ですからね。
頭をボコボコに殴られたあとに、私は病院へ行ってDVの恐ろしい実態を医者に話していました。しかしその頃は、私もまだ前夫をかばおうという意識があって、今の夫に付き添ってもらい病院に行ったのです。そのとき、彼は医者に呼ばれて「奥さんを殴ってはいけない」と叱られたそうです。今では笑い話ですが、殴ったのは別の人だと言いたかったのに、言えなかったということがありました。
DVのせいで今になっても尾を引いていることがたくさんあります。私の前夫は特殊な存在で公人でもあったので、彼から受けたDV被害については知る人は知るで、黙っていてくれたというか黙っていた人が多過ぎたので、今に至るまで前夫のDVについては表に出ていません。その後、DV法が施行されると聞いたとき、私は「やっとここまで来た」と思い、時代は確実に動いていると実感しました。
私が悩んでいたときはまだ、女は家庭に入っていればいい、男が世の中を牛耳っていればいい、と言われていたのです。昭和ひとけた世代の前の夫も、外では「女房、女房」と言って私を立てていましたが、内では暴君でいなければ気がすまない人でした。その世代が理想とする男性像を強く抱いていたのだろうと思います。それは彼の罪であると同時に、時代の罪であり、国の教育の罪であり、あるいはそういう大人に育てた母親の罪であったかもしれないと今になってそう思います。
DV被害を受けた経験から、私個人としては贅沢三昧な生活をするよりも、殴られたりぶたれることのない生活のほうが何倍もいいと実感しています。ときには苦労をして、お金のあった頃のほうがよかったと思うことが今でもあります。でも、物質的な安定よりも貧乏でもいいから幸せを感じる生活のほうがいいという考えは、年を重ねた今のほうが大きくなりました。
当時のメディアは今ほど堕落はしていなかったと思いますが、男性中心の、思想に裏づけされていた事はになめません。モラルとか道徳、あるいは暮らしぶりというものも男性の見方が非常に色濃く反映していたことは間違いなかったと思います。時代背景として、高度経済成長の真っ最中だったので、男たちが勢いづいていたということもあったかもしれません。
離婚発表の記者会見を開いてからの騒ぎの中で、メディアによって叩かれ、姑からは鬼だの蛇だの狐だのと言われて疎外され、悪妻の烙印を押されて汚名を着たまま自分の一生をズタズタにされて死んでいってもいいのかという、そのとき、私にとって非常に大きな課題を突きつけられたと思いました。
しかも、私は劇団を取り上げられて仕事をなくし、まさに兵糧攻めにあっているのです。挙句の果てに両親も追い出されてしまい、私が抱え込まなければならなくなりました。あちらを向いてもこちらを向いてもどっちを向いても、八方塞り。ドアというドアが次々にふさがれていくといった状況でした。
そんな状態で、まず、離婚というのは大きな部屋の隅っこで、一人ぼっちでじっと座り込んで考えなければいけない時間がくるのだ、それを最初に乗り越えなければいけないということを感じました。一人ぼっちの戦いから始まるのだと。
そういうときに私を救ってくれたものは何だったかと考えます。それは、ほかのことは何も言わずに、「こういう仕事があるけれど、やってみない?」と具体的な形で手を差し伸べてくれる仲間。ゴチャゴチャ言わずに、「好子さん、こうしようよ」と提案してくれる友人。それから「困ってるんじゃないのか?」と身の回りの生活用品をこっそり送ってくれる親戚…私は家を出たときの所持金が8,000円でしたから、すぐに1銭もない状況になってしまったのです。それから、「いつかこれで乾杯してね」という手紙を添えて、ベネチアングラスを贈ってくれた友人、といった人たちでした。こういう人たちの救いを受けたとき、私は一人で生きてきたのではなかったのだということをいやというほど実感しました。
問題はおばさん族かしら。「幸せなの?」、「恋してよかったじゃない」、「今、どうしてるの?」、「前の旦那さんはこう言ってるわよ」、「あなたが出て行った後、あの家はこうなったわよ」とうるさく話しかけてくるのです。私は彼女たちを幸せババアとそう呼んでいたくらいです。ます。他人に遠慮せずに入り込んではいろいろなことを聞いてくるのです。他人の人生にズカズカと入り込んでくるのが平気な人です。そういう人たちも含めて有象無象が近寄って来ました。
別れた夫にあとで聞いてわかったことですが、彼も同じようなことを考えていたのです。「好子さんはひどい女だった」とか「男癖が悪かった」と言ってくる人がいたし、劇団をもっていましたから、「先生の面倒を私が見たい」と写真付きで履歴書を送ってくる女優もいたそうです。有象無象がやってきたと、彼も話していました。
離婚とそれによって引き起こされた騒ぎの中で、私には自分たちが通ってきた世の中の縮図がすべて見えてしまいました。自分が離婚したわけでもないし、できないのに、離婚という人生のドラマに出演した気持ちになって擦り寄ってくる人間がいかに多いか。そういう人たちに翻弄されると自分を見失いそうになると思いました。
有名な女性占い師も出てきました。彼女は、先祖の祀(まつ)りができていないからとか、お墓参りをしてないからこんなことになったと言ってました。しかし、私はちゃんとやっていましたし、父も「うちにはそんなケチな先祖はいない。墓参りを怠ったぐらいで、うちの先祖は一生懸命暮らしている子孫をおとしめるようなことはしない」と言いました。こういう父がいてくれるのだからがんばろうと思いました。
こうして様々な苦労をしたなかから、女っていったい何なのか、妻っていったい何なのか、娘っていったい何なのかを考え、又、力がまかり通る世の中って何なのか、ここから重要なテーマが出てくるのではないかと考えました。そのときから、私は女性史をというより、女性の生き方を勉強し始めたのです。離婚がきっかけで大きなテーマをもらったこととなったのです。それまでは女性史をなぞって、女性にはこういう悲しい時代があったとか、こんなに偉い女性がいたといった、常に上のほうから下を見る日本の女性史のあり方が大嫌いで目を向けていなかったのです。
ところが有名な夫と離婚し、自分すら新しい女性史の対象にならざるをえないような状況になって、女性をテーマにして生きていくことはできないだろうかと思ったのです。それは私にとって、本当の意味での自立の始まりでした。
●生きるということ
自立するためには何かしらテーマがなければできません。同時に、自活という暮らすための経済力が伴うことも必要で、両方が自分の中に芽生えないかぎり一人では歩けないのです。一人で歩き始める準備ができれば、共感や共鳴してくれる人がやがて必ず現れます。それを力として生きていくしかないのです。暗闇の中で1本のロウソクの灯を頼りに、当てどのない方向に歩いていくしかない、 しかし、向こう側に光があることは確かだと無理にも思い込んでの再出発でした。もう後ろを見るのはやめよう、と思いました。これからのことを考えるには、今まで歩いてきた道だから後ろを見れば確実なのです。そして、未来にも光はなさそうです。
むしろ逆に、光を作っていくのが自分であり、そう考えたときに無我夢中で女性問題に立ち向かおうと決めました。別れた娘たちのために、自分の親のために、自分がどう生きてきたのかを考えようと思ったのです。でした。世の中のためにといったことはなおさら考えませんでした。世の中がいかに冷酷かということを知ったから、余計考えずにすんだのでしょう。
講演を頼まれると、演題が「夫と別れて元気に生きる姿」とか「元気印の好子さん」といったものを望まれることがありますが、正直言ってそんなことはありえないのです。しかし、食べていくためにはどんな演題だろうと聴衆が集まるかぎりは、引き受けざるをえませんでした。講演を依頼されて会場に行っても、「あなたみたいな、24年も連れ添った夫を平気で捨てる女性の講演を聴いても役に立たないから帰ってくれ」と、お金を叩きつけられて帰ったこともありました。
また、「好子さん、俺と付き合わないか」と猫なで声で擦り寄ってくる男もいました。まさに千差万別でした。それは逆に言うと、夫という存在がなくなったときに、お金を得ることがどれだけ大変かを教えてくれたのです。夫と一緒に無一文から出発したときの苦労ではなくて、女であるがためにあなどられるような苦労がついてきたという事です。
そんなとき、「もっとがんばらなくちゃね」と励ましてくれた人たちは、私より数倍も苦労した人たちでした。苦労をした人は苦労をしている人に、手を差し伸べようとしてくれるのです。そういった励ましを受けながら、社会の荒波に一歩一歩踏み出したとき、一つ、また一つと灯がついて、段々と足元が明るくなってくるという気持ちになりました。
さらに、身をもって体験する苦労と机上の苦労とは違うし、体験上からくる心配と言葉だけの心配も違うと知りました。命がけで生きてきた人が示すやさしさと、中途半端に人生を歩んできた人の励まし方はこれほど違うということも相当勉強しました。いくらうまいことを言ってきても、逃げる人は逃げますもの。
人間が生きていくというのは何なのでしょう。生きるってどういうことだろうというのも同様です。平和でお金があって、いい着物を着て、おいしいものを食べて、そして誰からも後ろ指を指されないように生きる、ということは人間にはありえません。あったとしても、それはそう見せているだけのことで、内側を見れば何も苦労のない人なんてこの世には一人もいないのです。
そう考えると、私たちは一つ一つやってくる苦労を受けて立つよりしょうがないのです。「こんなことが起きた」、「今度はこんな目にあった」、「いやになっちゃう。どうやって乗り切ろうか」、「こんなことが私にも起こるんだ」と思うとき、そのときやってきた苦労が実は私が生きることなのであり、苦労に立ち向かわざるを得ないのです。それは私に「これを乗り越えなさい」と教えてくれる苦労かもしれません。
しかし、常についてまわったのは、あれだけ仲が良かったと自認していたわたしたち夫婦でさえ最後は暴力によって亀裂が生じて別れてしまったという事実です。そもそも暴力とはいったい何なのかという思いでした。最初から暴力を振るう人はいません。何かがきっかけとなって、あるときから始まるのです。そして、一度暴力を振るうと必ず癖となり、続いてしまうという怖さです。
それはなぜでしょうか。様々な原因があると思うのですが、人が暴力を振るう姿が原風景にある人が一度暴力を振るうと、原風景の世界へ戻ってしまうということがあるようです。男性は我慢して我慢して世の中に出てきます。たぶん女性も同じでしょうが。しかし、我慢をしなくてもすむという状況になったときには、ひょいと、子供の自分に身近で起きた暴力のシーンを模倣しているということがあるのです。
だいたい偉くなり、世の中に認知されたあとに暴力が始まります。暴力でしか自分を表現できないという人は、最初から暴力を振るいます。
そして、暴力は人間が持っている理性を失わせますから、エスカレートしてドンドン激しくなります。それがどんな形で激しくなっていくかというと、まず征服欲がからんだ弱い者いじめ。暴力は強い者には絶対に向かっていきません。弱い者と決めた相手に向かっていくのです。これは自己顕示であり、自分の力の誇示であり、自分というものを確立していくための手段でもあります。これを、相手が弱い者であるときにしか発揮できないということを、暴力の定義の中に一つ入れておいてください。
男女関係の中で男たちは、あるいは夫婦という関係の中で夫たちは暴力を使ってきました。妻に暴力を振るっても、愛人には絶対暴力を振るわないという人がいます。それは愛人が自分に対して弱い立場にないということであり、妻は自分が養っているということを誇示するために、妻が言うことを聞かないと夫は暴力を振るうのです。
「愛しているからぶった」と前の夫が言っていました。でも、それは詭弁です。人は愛している人をぶつことは絶対にしません。なぜなら、ぶてば心が冷えることを知っているからです。
DV法が施行されて、かれこれ4年になるでしょうか。かつて女性解放運動をしていた団体がありました。男性を女性より下の存在と捉え、女性のほうが優秀だという考え方がちらつくその団体の運動は、その目的がたとえ女性の権利拡張や人権保護であっても私は嫌いでした。彼女たちの言動、風情(ふぜい)、顔つき、そして髪を振り乱して主張する口調、そのすべてが嫌いでした。その団体名を聞いただけで、げんなりしている時期がありました。
しかし、ときにはその団体もいいことをしてくれたのです。そこは、女性団体が人権問題を主題に活動した過渡期に現れた運動であり、中絶禁止法に反対しピル解禁を要求する団体も現れました。
今考えてみると、彼女たちは相当きちんとした運動をやっていたと思います。ピル解禁を訴えたその団体は、メディアで面白おかしく取り扱われていました。ピンクのヘルメットをかぶったメンバーが、女を泣かした男の会社や役所など、どこにでも行ってビラを配り、ピケをはり、拡声器で訴えるといった行動が話題になりました。そういった実力行使は、私たちにとって情熱的で切実なものだったのではないでしょうか。私は今になって、もっと応援してあげればよかったと思うのです。
結局、その女性解放団体の活動は、DVを公のものにするための大きなきっかけとなりました。1995年に北京で開催された第4回世界女性会議でも、家庭内の暴力について討議がなされ、それが引き金になったということもあると思います。多くの国の人々がDVについて、ついに声を上げ始めたのです。これは男女の別なく、洋の東西を問わず、あらゆる人々の声でした。そして、日本でもDV法の施行に向けて動き出すようになったのです。私はDVの法案ができたときに、これを勉強したいと思いました。
これまでDVに関する本を何度も書きました。しかし、出版社は相手にしてくれなかったのです。なかには本を刊行してくれた出版社もありましたが、今度は書店に卸す取次ぎ会社がまったく動かないのです。どうしてかというと、有名なベストセラー作家の別れた妻が書いている本だから。そして、自分たちの発行した雑誌であれだけ叩いた女性の本が売れたら困るから。さらに万が一、暴力を振るった前の夫が、実は有名なベストセラー作家だと知ったときの反応が心配だから。
「こんなリベラルな社会で、そんなことはありえないよ」と某出版社の方が言っていましたが、取次ぎに送った本が梱包した状態のままで返品されたときに、「あるんだね、こういうことが‥」と言って手を引いてしまうのです。今でもそういう状況は変わっていません。それでも、私はDVに関して最後の押しだと思い、DV法が施行される前に海外を見てまわることにしたのです。
●海外のDVの現状に学ぶ
まず、オーストラリアから始めて、中国、韓国、トルコなどに行ってきました。諸外国のDV状況はどうなっているのだろうか。DVの被害者と加害者に対してどういう扱いをしているのか。それでわかったのです。DVについては、日本が一番遅れています。
オーストラリアのメルボルンに行ってわかったことは、DV被害者の支援活動はいまやサービス業になっているということです。シェルターにも行きました。そこで何をしているかというと、自立プログラムでした。家を飛び出した女性のためのものです。その原因はどこの国も同じで、夫の暴力から逃れるため。これまで暴力に耐えていた理由は、子どもの存在と経済力がないことであり、この2点が解決しないから女性は自立できません。。
この国のすごいところは、女性が家を出たいと決めたときに国がお金を用意することです。そして、シェルターに入った女性には、今後どういうふうに自活して、どのように生きていくかのプログラムを作成します。作成にあたっては多くの人が関わります。
しかし、それには条件があり、その女性が自立できる能力を持っていること、権利を行使するだけでなく義務を果たす能力があることが必要なのです。つまり、国は自立を援助する用意はしているけれども、自分自身が自立に向かって努力を続ける覚悟があるかどうかが問われるのです。
これは日本とはまったく違う考え方だと私は思いました。日本のように、「困ったら飛んで来なさい。大変でしたね。これからがんばって」なんて言われ、中途半端な対処で終わることがないのです。そんな対処では、結局、妻は夫のもとへ帰らざるをえない状況を作ることになるし、戻った当初はおとなしかった夫が、しばらくすればまた暴力を振るうようになってしまいます。
オーストラリアではそんな曖昧な対処の仕方をしないのです。逃げてきた人に対して、何を不安に感じているかを尋ね、例えば家に置いてきたペットの犬や猫のことが心配だと言えば、ペットも保護してくれます。それが彼女の自立の妨げになればの話ですが。
こうした細かい点までが備わった上で、行政と手を組んでいる自立支援センターがオーストラリアにはあるのです。さらには、女性のための法案を作り、その法律に則った施策を目指す女性党という政党まであります。また、オーストラリアは多民族国家で、アラビア系、韓国系など様々です。男女間の問題は国によって考え方が異なり、差別的な部分もあります。共通なのがセックスです。この隠れた部分に関する問題を国がどうやって対処するか。それが国の未来にかかっていると認識しているようです。
多民族国家では、性的な慣習を国内で統一することはできません。しかし、誰にでもついてまわるのが性というものです。そしてDVは、性的な問題から起きています。だから、性的な部分をきれい事ですますということは解決にならないし、ありえないことなのです。
オーストラリアでは、そういった面にも取り組みながら、各州ごとに設けられた自立支援センターを運営しています。私も2、3ヵ所訪れましたが、規律は大変きびしいものでした。センターの200メートル以内に、夫もしくは恋人が立ち入れば、有無を言わせず逮捕されます。
さらに、センターを抜け出して夫のもとに帰ってしまった妻やセンターの所在地を教えてしまった人は、処罰を受けるのです。でも、それは当たり前のことで、本当に困っている人たちを守らなければいけないという決まりがあるのです。センターの方に私は言われました。「日本の女性が一番困る、自分の居場所をすぐ話してしまう」。これは悲しいかな、単一民族国家の悪いところです。もちろん、日本人女性の全部が全部そうだと言うわけではありません。
センターではあらゆる国の方たちが、自立を目指すためのプログラムを相談しながら行なっています。しかし、そこに行くことができないという人には、シドニーやメルボルンに女性だけの村が用意されています。この村は赤十字や市の応援を受けて過疎地に設けられたもので、村では縫製を教えたり、ハーブ栽培をして、洋服やハーブ関連の品物を販売しています。
この村を訪ねた男性との間に恋が芽生え、再婚する方もいるそうです。最初は本当に女性だけの村のつもりだったのが、やがて地域に密着していくわけで、国もそれを願っているようです。こういう動きは日本ではありません。
日本ではかわいそうな人を救ってあげるという意識の役所ばかり。しかし、役所だけでは救いきれないから、民間団体が存在するのです。その民間団体もカバーできなかった部分で事件が起きると、「知らなかった」とか「もっとちゃんとすればよかった」とか「申し訳ありません」と言って、関係者が頭を下げて終わりです。テレビでそういった光景を見ると、こんな国に何ができるものかと怒りたくなります。
お隣りの中国はどうかというと、もっときびしいです。私が行ったときには、ある夫婦間のDVが話題になっていました。それは世界的な心臓外科医が妻を殴り、堪忍袋の尾が切れた妻が訴えたというものでした。夫は妻の訴えを阻止しようと必死になったものの、何よりも妻の傷が事実を物語っていたのです。傷を受けて躊躇せず飛び込んだ妻の勝ちです。その結果、この世界的な医師は医師免許を剥奪され、国外に追放されてしまいました。
さらに、ある少数民族の女性のケース。彼女の村では、女は家畜同然の扱いを受けているのです。彼女は汽車で北京まで出て、北京大学へやってきました。実は北京大学では法学部が門戸を開いて、DVや児童虐待などに関してあらゆる法的な支援をしているのです。法律を学んでいる学生が被害者に代わって訴訟状を書き、本職の弁護士がそれを補佐します。だから、子どもが親を訴えることもできるし、DV被害者で教育を受けていない女性も駆け込むことが出来るのです。逆に言うと、大学側は実地で生徒に法律を教えていることになります。こんな大学は日本にありません。その後、学生たちは自分が扱っている事例をマスコミに流すかどうかを判断し、国選弁護士に依頼して裁判で勝訴を得ようとするまでも行動します。
中国では、日本のように児童虐待をしている親が開き直って、「子どもは自分のものだ」と連れて行ってしまうことはできません。中学生以上の子どもは、親から虐待を受けたら親を訴えられます。その訴えが認められれば、親といえども逮捕されるのです。中国人は東洋人だけれども、この中国の考え方はアメリカ人的とさえ言えます。
私が北京大学を訪れたときも、相談所の部屋に赤い紙がたくさん貼ってありました。これはすべてお礼状。私がいたときにも、駆け込んできた人がいました。その人の話では、身体に油をかけられて火をつけられた少数民族の女性がいるので、助けてほしいということでした。
オーストラリアでは毎年1回キャンペーンを行なっています。それは女性のためのもので、スローガンは「あなたの夫を疑いなさい」。夫というのは完璧な男性ではないと言っているわけです。そのスローガンを掲げて、長蛇の列のパレードが行なわれていました。
●全ての女性に必要なことは
女性が女性を助けるというのはどういうことなのでしょうか。女性が女性たちと生きるというのはどういうことなのでしょうか。そして、それを男性が補佐する社会はどういうことになっているのでしょうか。そこまで日本の法律は言及していません。
施行されたDV法は泣いています。本当に困っている女性、どうにもならないほど心が荒れきった女性がいるのです。DV被害を受けても、まだ考える余地のある人、まだ動けるだけの余地がある人は逃げてくればいいのです。ただし、逃げられる人は覚悟をもって逃げてくればいいのです。逃げ切れないのは人のせいにしているからです。「私には子どもがいるから逃げられない」、「私は経済力がないから逃げられない」と言って、留まっているというのが今の日本の現状です。
とはいっても、留まらざるをえないのです。それだけの用意が、社会にも、地域にも、もちろん国にもないのですから。そこに目をつけないかぎり、私たちはDV法からは何も得られないし、DV問題から解放されることはおそらくないと思います。
男女共同参画社会、いい言葉です。しかし、これに関しては予算がありません。例えば総理府の男女共同参画局が、なぜできたと思いますか。DV法がどんなお金で動いていると思いますか。実は売春禁止法の予算から出ているのです。男女共同参画局には何度も顔を出しました。「もっと動こうよ、もっときちんとやろうよ」と言いました。しかし、ここにあるのはデータだけです。女性の何%が殴られたとか、そういう数字ばかり。本当にやってほしいことは、国が民間団体と手を取り合って、身体と心を動かすような理性をもってやることです。命というのは身体と心と理性が伴うから命なのですから。
人権、財産、命、法律など守られているものは様々ですが、最も守られなければならないのは人の未来だと思います。それが伴わない人権というのはないのです。今、私たちが人権と言うときは、命が失われる、殺される、事故に遭うといった状況のときだけです。その人の未来の保障は人権に含まれていないのです。だから、私たちがやらなければいけないことをもっと手を広げていくべきなのです。しかしDV法は一つも活用されていません。
ボランティア活動についても誤解しているおばさんがいます。「暇だし、何か人の役に立つことでもやろうかしら」、そんな気持ちでボランティアをやってほしくないのです。ボランティア活動は、その人の生き方と競合していなければいけないと思います。相手に見返りを求めたり、自己満足のためにやるのはボランティア活動とは言えないのです。相手の立場になって、謙虚な姿勢でやるべきです。
「こんなにやってあげてるのに、感謝の念が足りないのよ」と言っている人はボランティアではありません。そういった勘違いをしている人が中心になって人を集めるから、当然他のメンバーも勘違いをするわけです。彼女たちの中から、先に述べたようなかしましババアが出てくるのです。勘違いしているボランティアは、たとえ100人いても必要ないと思います。
本気になって夫のもとから飛び出してきたら、その瞬間から孤独を友達として生きていかなければいけないし、そういう覚悟が必要です。どんなシェルターでも、コップがピカピカに磨いてあるところはありません。布団が干されているようすはありません。割れた茶碗、茶渋が付いたままの急須、汚れきった雑巾とタオル、部屋でただゴロゴロして寝ている女性、そんな状態では、まず、普通になる事のほうが大切だと実感しています。
自立の一歩は食器をきれいにすることから始めるべきなのでは。それは自分が使うからではなく、誰かが使う食器だからという意識を持たないかぎりシェルターに入ってはいけないと思います。そして、すべての女性たちに必要なことは、自立の心、自立の姿勢、自立への努力は、社会の中で鍛えられ、学び、実行されるものだという事です。
これを手助けするのが行政であり、ボランティアであり、施設であり、世の中が少しでも良くなるようにと考えている人々なのではないでしょうか。
今、この瞬間にも殴られている人はいるかもしれません。しかし、大概は夜です。人が眠っているときに殴られるからDVと言うのです。加害者は普通の人で、他人にはいい顔をしていて、世の中でも認められている人。そういう人が自分より弱い存在と決めつけた妻や恋人に向かう暴力だから、たちが悪いのです。子どもに向かった場合はもっとたちが悪くなります。
DV被害者の傷ついた心を解放してあげることが、今の日本ではできません。私は以前、DV被害の相談所を2年間ほどやっていたことがあります。これは全部申告制で、私なりのシステムで行ないました。「あなたはなぜ殴られると思うか?」「殴られているときの状況は?」、「未来に何をしたいと考えているのか?」、こういったことを作文に書いてもらいました。「上手な文章を書こうと思わなくていいから、現状がわかるように書いてください」と言いました。
作文を書いてもらうと、そこに答えが全部出ています。実際、書いたきりで来なくなる人も随分いました。しかし、行政に行くと被害状況をより具体的に書くことを求められ、医者に診てもらったかどうか、誰がDVを立証してくれるのか、すべて答えなければいけません。
DVを立証してくれる人については、何科の何という医者か、あるいは友人であればどこの誰かを聞かれます。立証する人が夫も妻も知っている場合、その半数ぐらいの人は夫に告げ口します。「あなたの奥さんはこういうところに相談に行ってるのよ」、「こういう弁護士がついているの」。親友というのは疑ってかかったほうがいいと思わざるをえません。特に、ご近所の親友というのは一番たちが悪いように思いますが偏見でしょうか。
私のところに来る相談者は、ほとんど地方の方でした。都会と違い、新しい人との出会いの場が限られてしまっています。そういところでDVの相談はうかつにできません。因習が深い成果、地方ではDVから殺人事件にまでいたるケースが多いのです。
相談内容によっては、カウンセラーをつけることがあります。しかし、日本には正式なカウンセラーは多くはいません。
なぜDVが起きるのか、現在はどんな状況か、解決のために何を乗り越えたらいいのか、その先あなたは未来をどう生きていきたいのか、という質問の後、対処しなければなりません。一人の人間の自立した人生と向き合うということは、その人のことを知るということではありません。その人がどう生きていくか、自分の未来をどのように描くか、それに手を貸すだけでいいのです。根掘り葉掘り聞いて「ひどい旦那だったね」とか言う必要はありません。DV被害者が今まで言いたくても言えなかった胸の内を吐露するという意味では、カウンセラーをつけることは当たっています。しかし、その前に自分で自分の人生を把握してみる必要があると思い、私は作文を書かせるのです。
DV法は実はまだしっかりと運用されていないというのが実感です。
まだまだ他人事という捉え方が一般的ですし、実際に自分の身に起きてみなけりれば、所詮は他人の事だという意識が日本人には多いのです。又、他人を思いやるという訓練もなされていない事も大きな原因であると思います。
幼児虐待と子守り唄
大人はともかくとして、子供に対しての虐待は救いようがありません。
虐待する側も手口も実に巧妙になってきています。虐待を他人にわからせない方法というのがあり、子どもの身体の中で、外から見えないところにタバコの火を押しつけたり、口の中に火のついたタバコを放り込んで口を閉じる、などは幼児虐待の一つの例です。警察は発表しません。毎日のように起こる虐待のすさまじさに時々無力感を感じてしまいます。救うことができないのです。救うためには、誰かが立ち上がらなければいけません。それがわたしであり、すべての大人たちでなくてはならないしかし、立ち上がるということができるか、が日本のこれからの課題になるのではないでしょうか。未来を担う子供たちのことは何より、優先課題なはずです。
大人たちは、子供達がそういうめに遭わないためにも、自分のDVにたちむかっていかなくてはなりませんよね。自分はそういう目に遭わない人でも、我が娘が、我が孫がいつ、遭うかも知れないのですから。
DV法というのは「私はDVを受けている」と最初に声を上げた人の勇気によって作られたと思っています。その最初に声を上げた人に、私たちは感謝すべきです。それは相当な勇気だったと思います。
このDV法をもっと有効に活用すべき時代が来ていると、私は思っています。地域や団体が本気になってDV法の活用に手を差し伸べ、未来の子どもたちのために女性を守ってほしいという基本方針を打ち出してくれることを願って止みません。命を生み、育て、守っていく役目を、母親は持っているのです。その母親が育児をきちんとしてくれればDVは自然に消滅するはずだと思い、また子守唄の活動をじゃまする人もいなくだろうとも考えています。すべての基本は、親子の絆のありように帰依すると考え、、日本子守唄協会を始めました。昔からの母親が伝えてきた子守唄をもう一度見直そうというのがその元で、三つ子の魂百までのいわれどおり、まず、家庭というあり方を見直す必要を感じているのです。世の中は大きな変わり目に来ていますし、それだけ、夫婦のありようや家族の形も違ってきています。しかし、うそのある家庭や取り繕うばかりの親おの形態では何も生み出さないという事は分かってきました。家庭も社会性をしっかり持っていないとだめという事でしょうか。しかし、社会性を身につけて教えている親はなかなか見つかりません。
親が何もかにもやってあげてしまうという家では、暴力に走る場合がおおいですね。
子守唄も、
以前は人は母親に刃物を振り下ろすなどということはありませんでした。今は、母親を考えただけで刃物を振り下ろしたり、暴力を振るったりしてしまいます。子どもに対して100%のことを要求するからお母さんは憎まれるのです。人間はどんなことでも半分しかわからないくらいにおもっていませんとね。
私は今、前の夫に対する態度を後悔しています。暴力を振るわれたときに、なぜ真綿でくるむように受け止めるような度量がなかったのだろうか。ほかにも、「なぜ、なぜ」と振り返ることは多いのです。責任がすべて相手にあるわけではなく、50%の責任は自分にもあるということも考えますと、若かっただけでは済まされませんもの。
しかし、DVの場合は覚せい剤などの薬や、本当に粗野な性格だとか、あるいは暴力が快楽になっている性的嗜好が原因になっていることもあります。その点をしっかりと見極め、把握して、この人と一緒では私の未来はないと判断したら、思いきって飛び出してくるべきです。留まってする苦労よりも、飛び出してからする苦労するほうに未来があるから。どうせ苦労するなら、未来のある苦労のほうがいいに決まっているくらいの覚悟は必要でしょう。。恥も外聞もかなぐり捨ててしまえば、人というのはけっこう気楽なものです。そこまでの決意をした人に対しては、DV法は生きてくるのではないかと思います。
DVの症例は限りなくあります。しかし、他人の症例を聞いても仕方がないじゃありませんか。殴られた痛みは当人しかわからないのです。DVの体験のない人から「わかるわ」と言われたって、そんなことありえません。「わかってたまるものか」と思います。
苦労話も話しているうちは大したことありません。もったいなくて他人には話せないのが本当の苦労です。簡単にわかってもらっては困ります。他人にはわからないほどの苦労をしたから、もったいなくて口に出せないのです。
苦労は財産なのです。私たちもそこまでにならないといけないと思います。そんなことを日々しみじみ感じて、自立と自活は双子の兄弟で、勇気は孤独と道連れで、実行は未来に灯をともします。このことを踏まえて、今日のお話の終わりとさせていただきます。
(終わり)
【プロフィール】西舘 好子
80年代に劇団を主宰。多くの演劇のプロデュースを手がけ、数々の賞を受賞する。その後、幼児虐待、DV(家庭内暴力)といった子どもや女性の問題に強い関心をもち、2000年には日本文化をかじる会、日本子守唄協会を設立。子守唄コンサートの主催、講演会、マスメディアへと活動の場を広げ、現在は、親子を再発見・再構築するプロジェクトを展開。
◆NPO法人日本子守唄協会代表、他
◆「修羅の棲む家」「男たちよ妻を殴って幸せですか?」「うたってよ子守唄」「子守唄の謎」など多数の著書